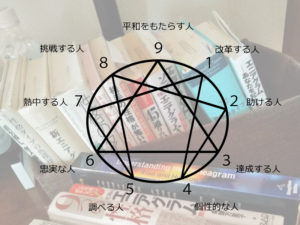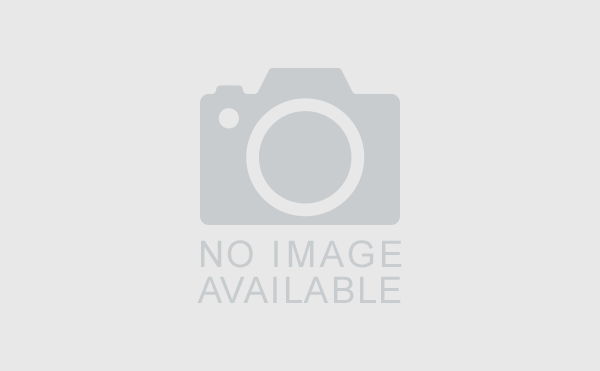ディベートとは何か?定義、効果、進め方、論理など全て解説
日本セルフコーチング協会では、コーチングのトレーニングの一環としてディベートを教えております。
コーチングとディベートは、水と油の関係だと思っている方もいるようですが、ディベートは使い方ひとつでコーチングスキルを高めることができます。
私はディベートのインストラクターです。
即興ディベート講座を開催したら、現役のコーチの方からの申し込みを頂き、その時にコーチングという仕事を知りました。
この記事では、そんなディベートについて一通り解説をしていきます。
ディベートとは何か?

geralt / Pixabay
ディベートの意味は、「討論」「討論をすること」です。
意見対立を前提にしたお題があり、そのお題を賛成する立場と反対する立場に分けて討論をしている状態をディベートといいます。
ディベートは口ケンカや言い負かしあいなのか?
それはケースバイケースです。確かに、口ケンカや言い負かしあいのようなディベートもあります。
例えば、「原発の稼働を続けるべきか?」というテーマがあって、賛成派と反対派に分かれて、双方が自分たちの意見を述べて、お互いの意見に反論しあえば、その時点でディベート成立です。
競技ディベート=説得力を競うゲーム
意見対立を前提にしたお題を用意して、肯定側と否定側の立場に分かれて第三者を説得する形で討論を行う。事前に決められたタイムテーブルにのっとり肯定側と否定側は交互にスピーチを行う。ディベートには、明確な勝敗があり、その基準は第三者を説得できたかで決まる
この4つの特徴があげられます。
- 明確なお題が用意されていること
- 肯定側と否定側に分かれること
- スピーチの時間・順番は固定
- 勝敗は第三者に委ねられる
条件1.意見対立を前提としたお題が用意されている
条件2.肯定側と否定側に分かれる
条件3.スピーチの時間・順番と役割が固定
条件4.勝敗は第三者(ジャッジ・観客)が決める
■その他、ローカルルール
ディベートの効果
ディベートの効果と誤解
ディベートは、教育関係者やコンサルタントの方から支持されています。
このような理由があるからでしょう。
- 論理力:道筋を立てて物事を考える力
- 論証力:物事を掘り下げて考える力
- 発言力:自分の意見や考えを的確に伝える
ディベートの試合をしていると、必ず論理的に物事を考えることが求められます。例外がありません。
また、ただ筋道を立てて物事を考えればよいわけではなく、ひとつひとつの論点を論証していく必要があります。
そして、これまで考えてきたことを自分の言葉で伝えなければなりません。
このようなトレーニングが行えるため、ディベートは重宝されています。
注意:ただし、目的もなく適当に議論をしているだけなら、逆効果の場合もあります。
ですが、今回はコーチングの技術を養うトレーニングの場として、いくつかアレンジをした形でディベートの効果についてお伝えしていきます。
ディベートだからこそ身につくこと
効果1.聴く→考える→まとめる→伝えるの技術を体得できる
ディベートの試合では、相手の主張を聴くところからスタートします。そして、相手の主張の弱点を検証して、その内容を体系的にまとめます。最後にまとめたことを自分の言葉で表現していきます。
たくさん話したほうが勝ちではなく、言葉のキャッチボールをするように相手の主張を聴いて上手に返すことが求められます。
コーチングやカウンセリングの基本動作として、傾聴、質問、承認のステップがあります。ディベートでは、反論こそしますが、その前提にあるのは傾聴を通じて相手の主張を理解するところからスタートします。その手順は何ら変わりません。
効果2.逆の視点から物事を考察・俯瞰することができる
あまり知られていないようですが、ディベートの試合では賛成側になるか、反対側になるかは試合直前までわかりません。あるテーマに対して自分は賛成なのに、反対側になったら反対側の意見を組み立てなければなりません。
よって、個人の価値観や好みを切り離し、どちらの立場になってもキチンと議論を組み立てる思考力を持っていなければなりません。このトレーニングが必然と相手の立場にたって物事を考えることにつながります。
例えば、あなたはクライアントに目標を達成してほしいと思っています。また、目標を達成することは素晴らしいと信じています。ですが、クライアントの様子を見る限り、目標達成をする意欲はないと感じました。
この場合、ディベートの思考力をもつことで、自分の意見や信念に囚われず、クライアントの立場で考えることもできるようになります。そして、相手の視点がわかるからこそ、適切なアプローチができるようになります。
効果3.意思決定や決断のトレーニングができる
これはセルフコーチングをしているときに効果を発揮します。
- 転職をするべきか?
- 起業するべきか?
- 〇〇さんとチームを組むべきか?
- 新しい事業を始めるべきか?
というテーマがあるとします。この場合、その行動をするメリットとデメリットの両方を用意して、客観的な立場から、その行動を実行するか否かの判断ができるようになります。このようなトレーニングは意思決定や決断をする場面でも大きな力を発揮します。
ディベートに向いている人・不向きな人
アカデミックディベートと即興ディベート
ディベートは大きく分けて2種類あります。
- アカデミックディベート
- 即興ディベート
前者は大学などで行われているリサーチ重視のディベートです。対して、後者は、話し方講座で行われているスピーチ重視のディベートです。
アカデミックと即興の違い
| アカデミックディベート | 即興ディベート | |
|---|---|---|
| お題 | 事前にアナウンスされる | 直前になって決められる |
| 取り組み | 2~3か月かけてリサーチをして試合に挑む | その場で議論を組み立てる |
| 論証方法 | 自分の主張を裏付けてくれる証拠資料集を作成する | 自分の言葉のみで立証していく |
| 勝敗の基準 | どれだけ議論全体が論証できたか? | どれだけスピーチの組み立てが上手にできたか? |
アカデミックディベートの特徴
事前にお題が発表されます。
例えば、「日本政府は、死刑を廃止するべきか、否か?」というテーマでディベートをすると仮定してください。
まず最初に、日本の死刑制度についてリサーチを行っていきます。インターネットのみならず、新聞や雑誌、専門書からその他の学術的な文献すべてに目を通していきます。
どれくらいリサーチをするかというと、その分野で専門家とお話ができるくらいの量が望ましいです。
リサーチをするだけではなく、そこから議論のカードを作成していきます。これを証拠資料集と呼びます。私も現役時代は、ワードで300ページくらいの資料集を作成しました。
即興で対応するのではなく、あらゆる議論のパターンを事前にシミュレーションして、相手がどんな主張をしてきても、問題なく対処できるレベルが望ましいです。中途半端なリサーチで試合をしても、試合では勝てないので、学生たちは必死になってリサーチをしています。
はじめたばかりは容量もつかめず大変かもしれませんが、1年くらい続けると段々と要領がつかめてきます。
即興ディベートの特徴
即興ディベートの場合、その場でテーマが発表されて、15分程度で議論を作成して、その場で一気に試合をします。準備時間は携帯電話/スマートフォンはオフにして、自分の言葉のみで議論を組み立てます。
そして、自分の言葉のみで自分たちの議論を発表したり、相手の議論に反論をしていきます。
アカデミックディベートに比べて、ファクトベース(証拠資料からの裏付け)よりも、スピーチの表現力や議論運びの上手さも評価の対象に加わります。(論理性は問われます)
より日常会話に近い感覚で説得力を競っていきます。
アカデミックと即興の比較
どちらも一長一短です。
ディベートそのものに興味があり、ディベートの技術を極めたい人はアカデミックディベートをお勧めしています。はじめの1年は苦労すると思いますが、その苦労を乗り越えた経験は財産になります。
一方で、相手に対してわかりやすく物事を伝えられるようになりたい。自分の言葉だけで説得できるようになりたいとお考えなら、間違いなく即興ディベートです。
コーチング向けの即興ディベート講座